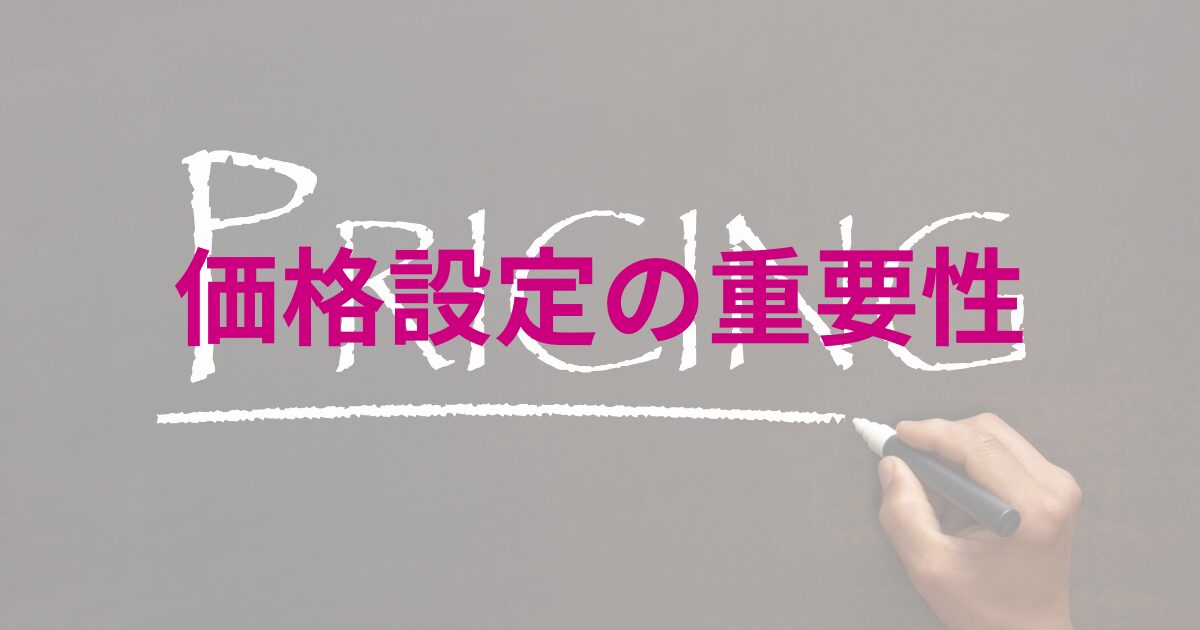「価格設定」で悩んだ経験はありませんか?
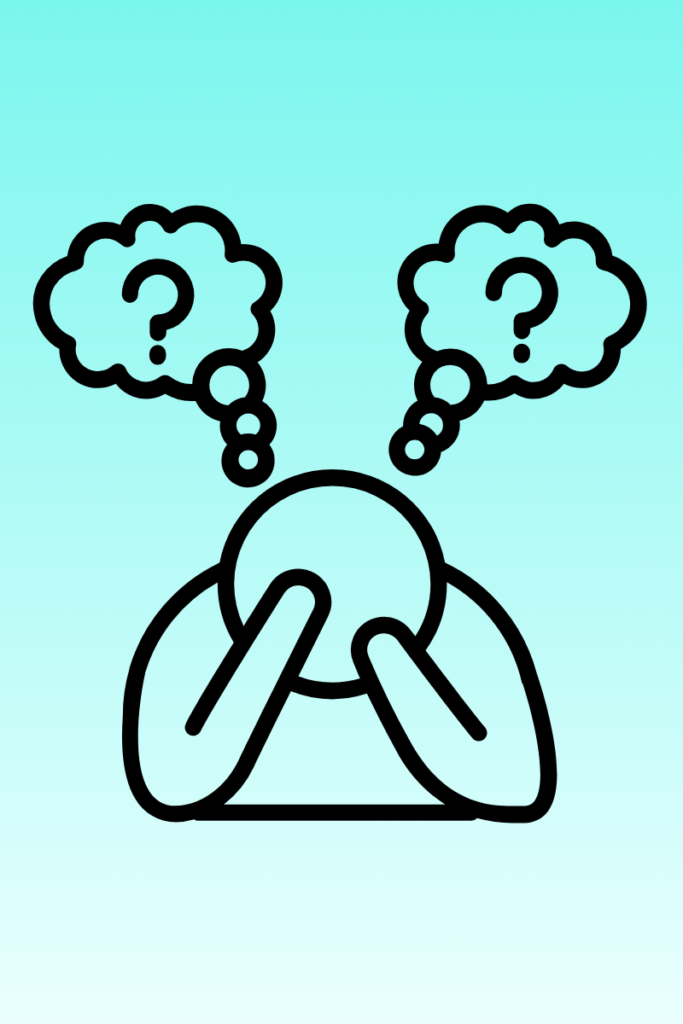
こんにちは。
みなさんは商品やサービスの価格を設定する時に迷った経験はありませんか?
新たに発売するときや、発売から時間が経ち価格変更を検討しなければなど、少なからず経験はあると思います。
私も同じく、数多く悩んだ経験があります。今回はそんな経験談を交えて、「価格変更」についておはなしをしていきたいと思います。
「売れない=値下げ」という短絡的思考
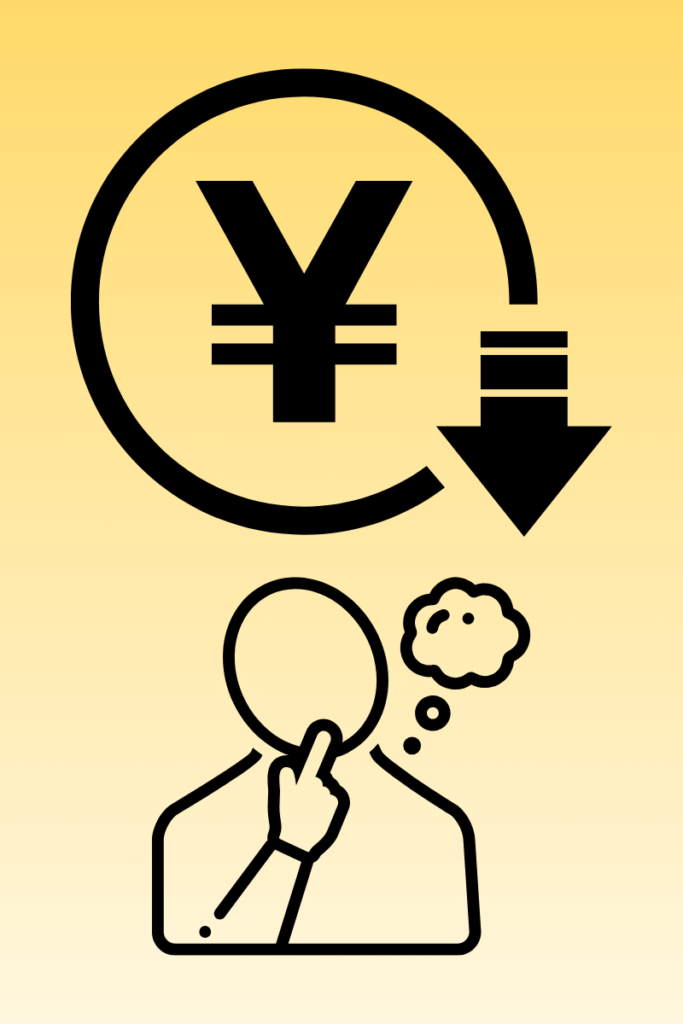
アパレル企業でマーチャンダイザー(MD)として働いていた頃、私は“値下げをすれば売れる”という思考にとらわれていました。
シーズン中盤に入って在庫が残ってくると、即座にセール対応。プロパー販売率よりも、いかに在庫を“はけさせるか”に注力していたのです。実際、セールを打てば数字は動きます。店舗でも「この値段ならなら買う!」という声が増え、売上グラフは一時的に右肩上がりになりました。
しかし、あるときからプロパー(定価)で売れる商品が極端に減っていきました。
「あの店は待てば安くなる」――顧客に刻まれた誤認識
次第に顧客からはこんな声を耳にするようになりました。
このブランドは、どうせすぐセールになるから、今は買わない。
顧客の購買タイミングは確実に“値下げ後”へと移行していたのです。結果的に以下のような悪循環に陥りました。
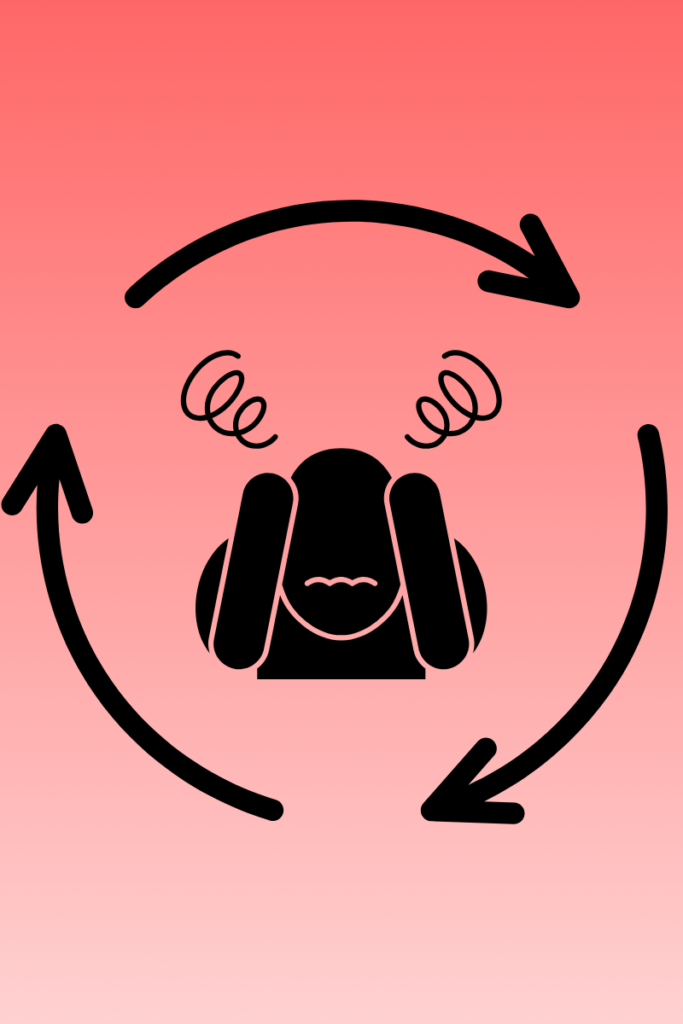
- プロパー消化率の低下
- ブランドイメージの毀損
- 値引き分の粗利圧縮
- 現場付帯作業の増加
- 次シーズンの価格戦略の混乱
少し待てば値下げされるブランドという印象を持たれてしまったら、いくら良い商品を作っても、顧客に対しての価値を生み出せません。新作商品の魅力も伝わらないのです。
「値下げ」への依存から抜け出せなくなる
値下げをすることにより、“売上”に対してのインパクトは大きくありました。しかし、そのインパクトは、本来得るはずの“利益”を減らすことにより成り立っているのです。
減った利益を上回る、売上をつくっていけば大丈夫だ。
気付けばこんな考えに陥っていました。この思考により、値下げをしなければ売上がつくれないと錯覚し、やめることが出来なくなりました。
“今売れる策”を打つことだけ。そうして毎シーズン、セール対象商品の選定に追われ、プロパー期に売るという前提が崩れていったのです。
売上をつくり続けるということは、試行錯誤を繰返した上に積み重なる結果です。当然ながらこの「値下げ」戦略は長くは続きませんでした。
価格戦略は「売れる価格」を決めることではない
本来、価格戦略とは以下のような複合的な視点で構築されるべきものです。
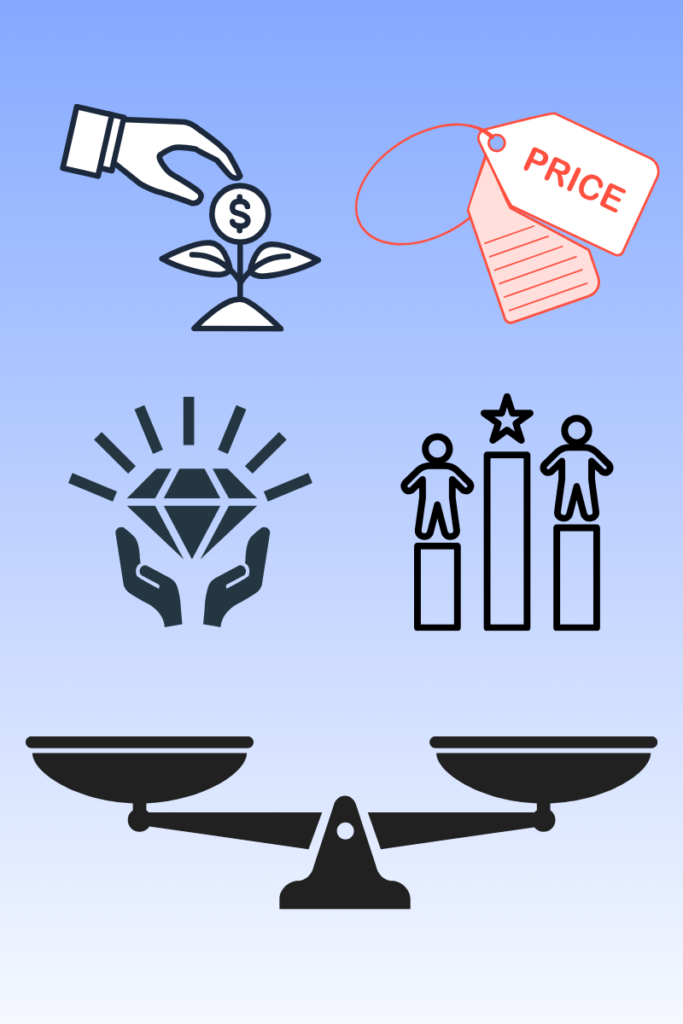
- 顧客が納得する価値とのバランス
- 競合との差別化をどう設計するか
- ブランド体験の一貫性をどう保つか
- 利益と継続性を両立させるか
たとえば、「素材にこだわったジャケット」であれば、そのこだわりを伝えるコンテンツや接客がなければ、価格に説得力が生まれません。値段が安いにこしたことはありませんが、本質は“顧客にとっての価値”を届けられるか、が重要なのです。
解決策:価格以外の価値を磨く
私はこの経験からから、単に「価格」ではなく、“価格を支える価値”を設計することに取り組み始めました。
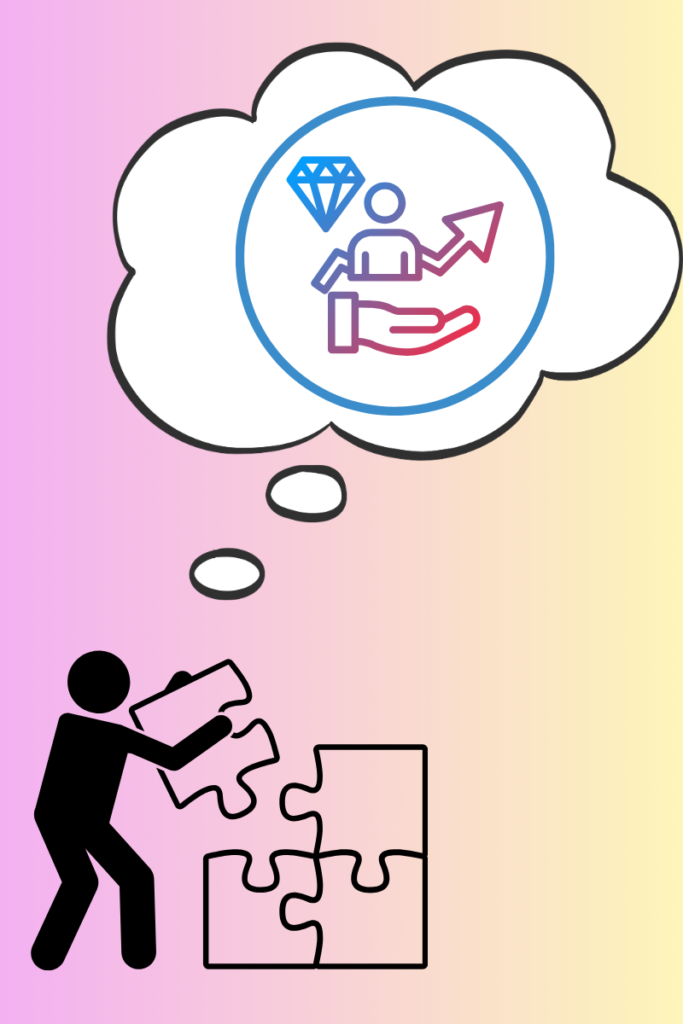
具体的には:
- 店頭スタッフによるスタイリング提案力を強化
- SNSやEC、メリット表示タグの取り付けなどで着用感や特徴の可視化
- 顧客ニーズの深掘り
- ブランドストーリーの構築
こうした施策を地道に積み重ねた結果、「定価でも買いたい」という顧客が少しずつ戻ってきました。もちろんですが、売上・利益のバランスを取りながら、あるべき姿へと戻るには相当な期間を要しました。
価格戦略に悩むすべての方へ
アパレルに限らず、小売・BtoCビジネスでは「価格設定」は売上を左右する極めて重要な意思決定です。
- 値下げに頼らず売るにはどうしたらよいか?
- 自社商品・サービスの“適正価格”はどこにあるのか?
- 顧客の期待値をどう操作すべきか?
こうした悩みに直面している方も多いはずです。そんな悩みを抱えている方へ向けて、参考になる無料資料を作成いたしました。是非ともご活用下さい!
まとめ|“価格”とは、伝えるべき「価値」のシグナル
価格は、単なる数字ではありません。
それは、ブランドが顧客に伝えたい「価値」のメッセージです。
戦略なき値下げは、短期的な売上と引き換えに、中長期的な信頼を失います。
だからこそ今、あなた自身のビジネスにとって「適正な価格とは何か」を問い直してみませんか?